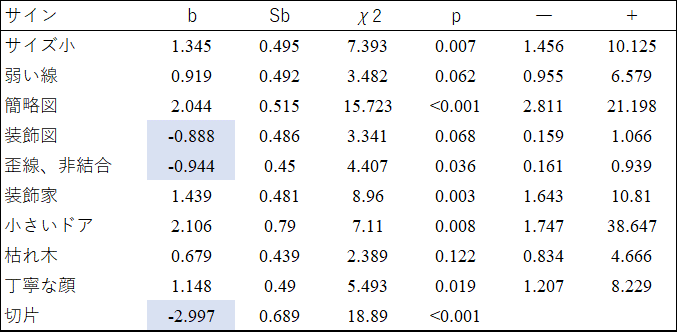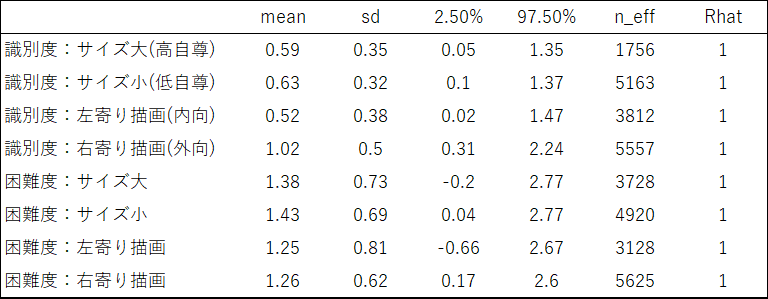0.窃盗の事例
主訴:繰り返し窃盗により逮捕された本児(以下:A)(高1)について、その再発防止と心理的援助を目的として心理担当職員が関りを開始
家族構成:A、母、兄、内縁男性
不適応行動について:小学校時代には自室で暴れて壁に穴をあけるといった行為があったが、他害はなし。中学校1年生の秋ごろに母の財布から数千円程度を持ち出すようになり、以後は兄、学校、アルバイト先と盗む対象を変遷させている。これまでに盗んだ金額についてAは詳細に覚えてはいないが大体40万円程度と語る。盗んだ金銭の使途は、漫画やゲームの購入に充てていた。その他の飲酒、喫煙などの逸脱行動は行っていないといい、万引きについても「ばれる可能性が高いと思うから」という理由で行っていないとのこと。犯行についてはは単独犯であり、仲間に誘われて実行に至った等の構図はない。
検査:WISC-Ⅳ 全検査:110 下位尺度もほぼ同様の値
被虐待経験について:日常的な虐待状況を窺わせるようなものはない。
家族について:自身を愛しているのか不安に思う一方で、自分を気遣ってくれて優しい母と話す等、同居中の家族の中では実母に対して一番の思慕感を示している。同居中の男性は突如事実上の内縁男性となったことで、戸惑いがあった。被虐待経験のある母はAへの愛情の示し方に戸惑うことが多く、「冷たい接し方が多くなった」と語っていた。母からは「何を考えているのか分からない子」など、Aの主張性の低さがうかがえるエピソードが出ていた。
家庭での様子:些細な失敗で懲罰的に制限が強化され、自由が徐々に奪われる間隔を持っておりストレスが蓄積していった。加えて母からA自身への愛情に対する不安があった時期に、Aから見て好印象な男性が急に同居し、事実上母の内縁男性となったことへの困惑があり、母と同居人とのことで複雑な思いを消化できずにいた。
友人関係:「A県は東北と違って遊ぶのにお金がいる(からお金を盗んだ)」「目立ちたくないのに、転校生ってことで嫌でも目立った」と話していた。東北との友人関係の差異に戸惑っていたことに加え、集団から浮くことへの強い不安感を覚え、集団から浮かないように同調しようとした結果、お金が必要な場面で窃盗を働いてしまうという構図があった様子。また自宅の近所に親友と呼べる特別仲の良い友人がおり、その友人が様々なものを持っており、ゲームなどの物を介した関りが中心だったとのこと。その友人との関係を切らしたくない思いが強かったようで、それも金銭窃盗の動機の1つであった可能性は否定できない。
学校関係:学業は問題なし。部活動は参加していたが窃盗発覚により退部。休日はやることが無くて盗んだゲームで遊んでいたと話す。
1.窃盗とは何か
◆窃盗の定義と法定刑
窃盗とは、他人の財物を故意に持ち去ることをいいます。
刑法における窃盗罪では10年以下の懲役又は50万円以下の罰金の法定刑が科されます。
◆病的窃盗(DSM-5)の診断基準
A.個人的に用いるためでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく、物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される
B.窃盗に及ぶ直前の緊張の高まり
C.窃盗に及ぶときの快感、満足、又は開放感
D.その盗みは、怒りまたは報復を表現するためのものではなく、妄想または幻覚への反応でもない
E.その盗みは、素行症、躁病エピソード、または反社会性パーソナリティ障害ではうまく説明されない
となっています。窃盗行為自体が目的となっており、窃盗実行前実行中に快の感覚があるなどが特徴となっています。
◆盗みの人口統計学
男子の50%と女子の32%が、小学校以来少なくとも1度か2度他人のものを盗んだことを認め、数回の盗みを認めた回答者は少なく(男子=11%、女子=4%)、さらに数回以上の盗みを認めた回答者も少なかった(男子=2%、女子=1%)ことを報告しています(Slocum & Stone ,1963)。全体の盗みの有病率は15.2% (Grant, Potenza, Krishnan-Sarin, Cavallo, & Desai ,2011)、であるという報告や、万引きの母集団レベルの推定値は、成人で11.3%、青年で15%という報告があり(Blanco et al., 2008)、全国万引き防止協会(2019)によると、消費者の11人に1人は万引きをしていると考えられています。窃盗行為自体は、極端に珍しいものではなさそうです。
2.窃盗に至る背景にはどのようなリスク因子があるのか
窃盗行為(盗みと表現する箇所が多々あってすいません)に関連するリスクなどを示す先行研究が多くありますので、以下にまとめていきたいと思います。
◆盗みの定着
少なくとも3~4か月に1回捕まる割合で5歳から10歳にかけてこの行動を継続することは問題であると特徴づけられている(Patterson, 1982)。Baruah(1989)は、7〜8歳を問題窃盗のカットオフとすることを提唱している。しつこく盗みをする人は、保護者や学校が行う罰、店からの追放、逮捕など、加害者にとって様々なリスクがあるにもかかわらず、その行動を維持する。おそらく、捕まる確率が低いことが一因で(例, Baumer & Rosenbaum, 1984; Belson, 1975/1976; Griffin, 1984; Hood & Sparks, 1970; Ingamells & Epston, 2013; Shapl&, 1978)、ましてや逮捕されて有罪になる可能性も低い(Akers, 1973; Farrington, 1973; National Association for Shoplifting Prevention, 2019; West & Farrington, 1977)。窃盗が個人のレパートリーの一部として根強く定着するメカニズムを説明する上で、Akers(1973、p.197)は、"プロの犯罪者は時に捕まり処罰されるが、犯罪の継続に対する強化の頻度と確率、量は、この散発的で不確実な処罰よりもはるかに大きい "と述べており、B&ura & Walters (1959, p. 365)は、"多くの場合、継続的な犯罪者は、受ける各罰の間にかなりの報酬を蓄積していることが明らかである "と見解を示している。
◆盗みの他因子との関連
子どもや青年における盗みは、他の様々な逸脱的トポグラフィー(例えば、破壊行為、身体的攻撃、未成年者の飲酒、逃亡、不登校など)と組み合わされた場合、成人の反社会的行動(Farrington, 2005; Robins, 1978; Robins, 1986; Robins & Ratcliff, 1978)と健康・職業上の困難(Robins, 1986)を予測する。また、幼少期の窃盗と非行、学業成績、精神病理学の問題との関連性を指摘する者もいる (Farrington, 1973; Krohn & Thornberry, 2003; Loeber, 1982; Loeber & Dishion, 1983; Mitchell & Rosa, 1981; Moffitt, Caspi, Harrington, & Milne, 2002; Moncher & Miller, 1999; Robins, 1978)。喫煙、薬物の使用、攻撃的行動、認知的困難、衝動性も窃盗と関連している (Baylé, Caci, Millet, Richa, & Olié, 2003; Grant et al., 2012a; Grant et al., 2011; Greening, 1997; Patterson, 1982)。
Austin et al.(2018)では盗癖者の窃盗行動と衝動性の関連について、万引きで逮捕された病的窃盗患者では、衝動性については有意ではないものの関連が示唆されており、その効果量は大きいか非常に大きいことが示された。仮説に反して、万引きで逮捕された者は、万引きで逮捕されなかった者に比べて、窃盗行為の頻度や病的窃盗の重症度が有意に高くなることはなかった。
Grant et al(2015)では大学生における窃盗の特徴について、盗み後の精神的落ち着きは得られていないものの、不十分な衝動制御の問題(強迫的な性行動、抜毛等)と関連しており、また双極性障害や抑うつ症状の悪化、認知されたストレスレベルの上昇などとも関連していることが示唆されている。
◆親の監護との関連
Ho(2007)は親の監護と、盗みを含む反社会的行動(AAB:盗み、嘘をつく、いじめなどの行為から構成)との関連について報告している。親の監視不足と思春期の疎外感は、人口統計学や他の子育て指標を制御した後、AABと関連することが観察された。子どもの居場所や行動をよく知っている親は、AABの子どもを持つ確率が低い。親から疎外されていると感じている青年は、親から受け入れられていると感じている青年に比べ、AABが高い。貧しい家族の力学は親の監視とAABとの関連を媒介するようであり、反抗期は親の監視とAABによる思春期の疎外感との関連を媒介するようである。
◆犯罪行動の心理学的側面
犯罪行動の心理学の側面から、犯罪行動のリスク因子の側面から考えます。代表的なものにセントラルエイト リスク・ニーズ要因(Bonta & Andrews,2017)があり、犯罪歴、犯罪指向的態度、犯罪指向的交友、反社会的パーソナリティ・パターン、家族・夫婦、学校・仕事、物質乱用、レジャー・レクリエーションの8つが犯罪行動のリスク因子になるというものです。
3.窃盗行為自体にはどのような意味・機能があるのか
窃盗行為は、盗みを働く人にとって何かしらの意味があるから行うし、何かしらの意味があるからそれを続けるわけです。窃盗をする人も、その行為が犯罪であり、自分にとってリスクがあることは重々理解しています。それでもなお、どうして窃盗を行い、一部の人は続けてしまうのでしょうか。
◆盗みの機能
盗みを調査した研究者が提示した経験的根拠のある行動指向の仮説と、他の問題行動に対する既知の機能(Beaversら, 2013; Hanleyら, 2003; Iwataら, 1994c)を考慮すると、盗みの機能として一般的に3つが考えられるようである。
1.最も経験的な裏付けがあり(まだ限定的)、ほとんどのケースに適用できそうな盗みの機能は、盗まれた品物への直接的で非介入的なアクセスによる維持(非社会的機能)である。このような場合、不正に入手した(そして表向きは操作または消費された)品物は、社会的変数による寄与なしに、盗みの構成反応を強化する役割を果たす。
2.2つ目の盗みの機能として考えられるのは、広義の社会的機能であり、様々な手段で様々な種類の正の強化(例えば、注目、物品、金銭)を媒介として獲得することである。重要なことは、注意の機能が疑われる場合でも、取られた品物の潜在的な強化価値を考慮することである(すなわち、多重支配が可能である)。これには、仲間に良い印象を与えようとしたり(例えば、友好的な挑戦、他人に盗んだものを自慢したり見せびらかしたり、愛情や地位を得るために他人に贈ったり)、盗んだ金品を他の人と交換して追加の品物や金銭を得たり、あるいは大切なセラピスト、教師、養育者などによるカウンセリングや戒めを通じて注意を受けたりすることが含まれるかもしれません。
3.おそらく最も可能性の低い窃盗の機能として、社会的な負の強化が挙げられる。仲間からのプレッシャーや暴行・盗難・その他の不快な出来事の被害者といった回避的な社会現象によって引き起こされる盗み(すなわち、報復的盗み)の実証実験は不足しているが、そのような例は一般文献に頻繁に記載されており、直感的に理解することが可能である。
盗みは、一般に報告されている多くの行動問題(例えば、攻撃性、破壊的行動など)とは異なり、有形物への直接的、非介入的なアクセスをもたらすという点で特異である。以下では、行動分析学的な視点に最も適合し、社会的強化と非社会的・自動的強化の源の既存の分類法と一致する、現存する文献で示唆されている機能を中心に、考えられる盗み機能の概要を説明する(Hanleyら、2003;Iwata et al.,1982/1994を参照)。
窃盗に関しては、Akers (1973, pp. 196-197)は、“職業的窃盗は金銭的見返りという正の強化だけでなく、認知、名声、他の窃盗犯との同一性や警察や他の人からの尊敬という社会的強化によって維持されている”と記述している。また、Leung et al. (1992)では、認知や名声は、友人や潜在的な友人からの承認を得るために盗難後に「贈与」することを含む可能性のある、子どもの頃の盗みの要因として挙げられている。
仲間からの認識、承認、受容、名声の獲得は、おそらく盗みとの関係では遅れるものの、注目へのアクセスによって強化される行動という概念と概ね適合すると思われる。Renshaw(1977)が盗みの原因を解明するために行った広範な取り組みには、盗品を贈ることで仲間の愛情を得ようとする試み、仲間や反社会的家族から承認や注目を得ようとする試み、社会的挑戦や挑戦によって引き起こされる盗み(その他の経験的根拠の乏しい原因)などが含まれている。あえての挑戦や社会的挑戦は、ピアプレッシャーの概念と一致し、正の強化(例:挑戦完了後に仲間から賞賛を受ける)と負の強化(例:指定された反応を完了したら挑戦を打ち切る)の両方の側面を含む場合があることに注意することが重要である。窃盗の維持変数としての社会的強化は、青少年が時に仲間の共犯者と一緒に窃盗をしたり、仲間に不正行為を報告したり、仲間に盗品を配ったりするという報告からも示唆されている(Brooks & Snow, 1972; Buckle & Farrington, 1984; Miller & Klungness, 1989を参照)。
Wetzel(1966)では、10歳の少年の盗みは、注目(ケースワーカーに自分の行動を説明する試みを含む)へのアクセスによって強化されることが記述的情報から示唆された。Luiselli & Pine(1999)は、10歳の女児が盗みを行った際、その行動に関して大人と長時間話し合うことで強化されると仮定している。機能ベースの治療パッケージ(盗みに関する議論の差し控えを含む)は、盗みの減少に関連していた(ただし、行動は、大人との議論によって強化された)。
社会的圧力や仲間からの圧力といった回避的な社会的刺激に反応して個人が盗みを行う場合(例えば、Farrington, 1973/1999; Moore, 1984; Nadeau et al, 2019; Schwartz, & Wood, 1991)、おそらく悪戯の終了や脅威の撤回につながる負の強化機能が働いている可能性がありる。報復や復讐として機能する盗みのような反コントロールも示唆されている(Arboleda-Florez, Durie, & Costello, 1977; Bauer, 1973; Bettleheim, 1985; Gerlinghoff & Backmund, 1987; Leung et al, 1992; Miller & Klungness, 1989; Moler, 1977; Renshaw, 1977; Schlueter et al, 1989)。つまり、表向きには、攻撃や盗みなどの不快な社会現象の犠牲となったときに盗みが誘発される可能性がある。このような場合、報復的盗みの強化因子は先行する不快な社会的刺激の除去であると考えられるが、被害者になってから復讐するまでの時間的不連続性は他の可能性(例えば、ルール・ガバナンス)を示唆している。
窃盗は強化子を直接生み出すため、「自己強化性」(Henderson, 1981; Stumphauzer, 1976)と特徴づけられてきた。自動強化(Vaughan & Michael, 1982; Vollmer, 1994)という用語は、社会的仲介なしに行動が持続し、明らかな社会的結果を伴わない盗みがこのように維持される行動と一致するように思われる場合に適用される。社会的随伴性がない状態で維持されていると思われる盗みの最も明確な例は、個体が一人になったときに(例えば、別の観察室から)埋め込まれた食物を取ることが観察された研究から得られる(例えば、Simmonset al.,2019)。これらの一見バラバラな反応に共通するのは、他の個体による強化子の配給がないことである。 盗まれたもの(およびその消費または操作)への直接アクセスを暗示するのとは対照的に、一般的な文献では、挑戦、スリル、興奮を経由して盗みが強化されることがあるという理論が一般的である。
社会的媒介を受けないスリル追求としての盗みは、自動強化の概念と一致する。人口の0.3~0.6%に診断される、明らかにまれなタイプの衝動制御障害である病的窃盗は、(単独行動で)不要なものを盗みたいという衝動に一貫して抵抗できない個人につけられるラベルです(DSM-5、アメリカ精神医学会、2013年)。報告によると、病的窃盗と診断された人は、精神医学的問題を併発していることが多く、盗みに際して一種の心理的救済やその他の付随する感情を経験し(例えば、Grantら, 2012b; Goldman, 1991; Krasnovsky & Lane, 1998; Marzagão, 1972; McNeilly & Burke, 1998; Olbrich, Jahn, & Stengler, 2019)、精神分析系の「内的メカニズム」が関与している(Goldman, 1991)。病的窃盗における緊張や不安は、盗む直前に喚起的に起こると考えられていることは興味深い(例えば、Goldman, 1991; Grant et al., 2012b; Mouaffak, Hamzaoui, Kebir, & Laqueille, 2020; Olbrich et al., 2019)。しかし、そのような緊張が盗用機会とは無関係に生じるのか、それとも盗用機会にのみ反応するのかは不明である。
4.窃盗行為はどのように始まり、変化していくのか
窃盗行為の具体的な意味づけは、窃盗の開始時から変わっていくことは珍しくありません。どのように変化していくのでしょうか。以下、浅見他(2021)を中心に見ていきたいと思います。
◆病的窃盗の発症過程における認知と行動の変化(浅見他,2021)から引用
病的窃盗の移行過程全体の動き 病的窃盗の移行過程については,まず,万引きの生起段階として,初めて窃盗行動を行う行動の開始の段階,そして,窃盗行動の頻度が拡大する行動頻度拡大の段階を経て,病的窃盗の依存段階へと移る。
病的窃盗の依存段階においては,窃盗行動への従事そのものから得られるメリットが物品獲得のメリットを上回る病的窃盗の段階,習慣化していつもの店で自動的に窃盗行動が引き起こされる窃盗の自動化の段階という4 つの質的に異なる段階を内包したモデルが作成された。
行動の開始 病的窃盗患者,万引き経験者,ともに行動の開始の段階においては,「物品獲得が主目的」という点で同様の機能が確認された。小学校入学前の幼児期に窃盗行動を開始した者は,盗むことが悪いことという学習が十分になされていない状態で,,物品獲得そのものをメリットに感じたという随伴性が確認された。小学生から19 歳までの児童期から青年期に窃盗行動を開始した者は,「友人の誘い,身近な成功例」をきっかけにして物品獲得そのものをメリットと感じたという随伴性が確認された。20 歳以上の成年期以降に初めて窃盗行動をした者は,「窃盗衝動が規範意識との葛藤に勝ってとる」ことが語られ,衝動的にとってしまい,物品獲得そのものをメリットと感じたという随伴性が確認された。
行動頻度拡大 「罪悪感が薄れ,ばれない工夫をする」ようになっていく。さらに,促進要因として,精神疾患などの影響から物をため込むことで安心感を得たり,家庭や学校における孤立を避けるため過度に周囲に合わせて自己抑制したりする「ためこみ癖,過剰な適応」などの影響もあって,窃盗行動によって得られるメリットとして,物品獲得のほか,スリルやストレス発散など種類が増えて,「窃盗の意味が拡大する」こととなる。
病的窃盗 万引きの生起段階として窃盗行動を繰り返しているうちに,病的窃盗の診断基準に相当する状態へと移行がみられた。第一段階として,窃盗行動によって得られる物品よりも,窃盗行動への従事そのものによって得られるメリットが大きくなる病的窃盗の段階がある。この段階においては,精神疾患などの影響から「慢性的な不快情動,快情動の消失」がある際に,「ストレス発散,不安低減,現実逃避」や,「スリル,達成感,高揚感」,「あてつけ,他者の関心」といった行動自体から得られるメリットが主目的となる。窃盗行動をやめることはできずに,自分を責めたり,人との交流を避けたりすることがさらに慢性的な不快情動の出現や快情動の消失につながっていく悪循環に陥っていた。
窃盗の自動化 窃盗行動をそのまま繰り返して続けているうちに,窃盗の自動化段階に進んでいる者もいた。「とらないことがストレス」となり,いつもの店に入り,「とれる条件がそろうといつでもとる」というように,明確に意識しないまま窃盗行動を繰り返す状態になっていることが明らかにされた。病的窃盗段階と窃盗の自動化段階においては病的窃盗の診断基準に該当し,病的窃盗の依存段階にあたると考えられる。
<年代に応じた再犯防止対策>
幼児期においては,窃盗はしてはいけないことであるという知識としての規範意識がそもそも十分に形成されておらず,この段階の窃盗行動は早期発見と窃盗はしてはいけないことだという規範意識の形成による効果が見出しやすいと考えられる。児童期から青年期においては,窃盗はしてはいけないことであるという規範意識は知識として保持されていたため,発覚しないように周囲を気にするものの,成功例や友人の誘いをきっかけに遊び半分で安易に行っていることが明らにされた。そのため,大久保他(2013)が指摘するように,万引きのきっかけを作らせない家族との良い関係性や万引きされにくい店づくり,さらに,万引きの結果としてどのような事態を招きうるかという点の学習などの有効性が期待できる。成年期以降においては,病的窃盗以外の精神疾患の症状や経済状況の悪化といったマクロ的状況と規範意識との間の葛藤が語られており,道徳教育や刑罰のみでは窃盗行動をやめることは相当に難しいと考えられる。そのため,精神疾患の治療や経済困窮に対する支援などが万引きの再発防止に寄与すると考えられる。
5.窃盗児童Aのアセスメントと対応
改めて窃盗児童Aの事例を掲載します。
主訴:繰り返し窃盗により逮捕された本児(以下:A)(高1)について、その再発防止と心理的援助を目的として心理担当職員が関りを開始
家族構成:A、母、兄、内縁男性
不適応行動について:小学校時代には自室で暴れて壁に穴をあけるといった行為があったが、他害はなし。中学校1年生の秋ごろに母の財布から数千円程度を持ち出すようになり、以後は兄、学校、アルバイト先と盗む対象を変遷させている。これまでに盗んだ金額についてAは詳細に覚えてはいないが大体40万円程度と語る。盗んだ金銭の使途は、漫画やゲームの購入に充てていた。その他の飲酒、喫煙などの逸脱行動は行っていないといい、万引きについても「ばれる可能性が高いと思うから」という理由で行っていないとのこと。犯行についてはは単独犯であり、仲間に誘われて実行に至った等の構図はない。
検査:WISC-Ⅳ 全検査:110 下位尺度もほぼ同様の値
被虐待経験について:日常的な虐待状況を窺わせるようなものはない。
家族について:自身を愛しているのか不安に思う一方で、自分を気遣ってくれて優しい母と話す等、同居中の家族の中では実母に対して一番の思慕感を示している。同居中の男性は突如事実上の内縁男性となったことで、戸惑いがあった。被虐待経験のある母はAへの愛情の示し方に戸惑うことが多く、「冷たい接し方が多くなった」と語っていた。母からは「何を考えているのか分からない子」など、Aの主張性の低さがうかがえるエピソードが出ていた。
家庭での様子:些細な失敗で懲罰的に制限が強化され、自由が徐々に奪われる間隔を持っておりストレスが蓄積していった。加えて母からA自身への愛情に対する不安があった時期に、Aから見て好印象な男性が急に同居し、事実上母の内縁男性となったことへの困惑があり、母と同居人とのことで複雑な思いを消化できずにいた。
友人関係:「A県は東北と違って遊ぶのにお金がいる(からお金を盗んだ)」「目立ちたくないのに、転校生ってことで嫌でも目立った」と話していた。東北との友人関係の差異に戸惑っていたことに加え、集団から浮くことへの強い不安感を覚え、集団から浮かないように同調しようとした結果、お金が必要な場面で窃盗を働いてしまうという構図があった様子。また自宅の近所に親友と呼べる特別仲の良い友人がおり、その友人が様々なものを持っており、ゲームなどの物を介した関りが中心だったとのこと。その友人との関係を切らしたくない思いが強かったようで、それも金銭窃盗の動機の1つであった可能性は否定できない。
学校関係:学業は問題なし。部活動は参加していたが窃盗発覚により退部。休日はやることが無くて盗んだゲームで遊んでいたと話す。
前述までは、いわゆる窃盗ケースについての一般論です。
ここからは、本ケースという個別事例に焦点化して、窃盗行為の開始やその維持要因について、機能分析の観点から見立てていきたいと思います。
1.窃盗の開始と盗みの機能
金銭窃盗のきっかけとしては友人関係の維持を目的として行為に及んだというものである。その根っこにはAのもつ当時のストレス構造があり、理由として①友人関係の維持以外にも、②父母の離婚、③家庭での制限の強さと母からの愛情に対する不安、④母と同居人の関係性への思いの4点があった。しかしそのストレスについて、母の共感的受容力の低さと母に受け止めてもらえるかの不安、友人関係の希薄さにAの自己主張性の低さが相まって、他者に言語化できずにストレスを蓄積させていったという状況があった。以上により、本ケースにおける盗みの機能としては「広義の社会的機能」であったと考えられる。
①友人関係の維持について、窃盗の維持変数としての社会的強化は、仲間に盗品を配ったりする(Brooks & Snow, 1972; Buckle & Farrington, 1984; Miller & Klungness, 1989を参照)、窃盗品を贈与することで友人からの認知や名声を得る(Leung et al. ,1992)という報告から示唆されている。
②~④に共通する家庭内での孤立感について、反抗期は親の監視と反社会的行動(AAB:盗み、嘘をつく、いじめなどの行為から構成)による思春期の疎外感との関連を媒介する(Ho,2007)という先行研究があり、本ケースにも当てはまる。いわゆる「寂しくて物を盗む」と(正直根拠に乏しいと感じる)心理の先輩から脈々と言われてきたオカルトは、本先行研究なんかが近い知見を示しているのかもしれない。
つまり窃盗の開始については、父母の離婚や母の制限等のストレスがあったが、母の共感的受容力の低さと母に受け止めてもらえるかの不安、友人関係の希薄さにAの自己主張性の低さが相まって、他者に言語化できずにストレスを蓄積させていったという状況があり、希薄な友人関係を維持するために窃盗を用い始めた、と考えられた。
2.窃盗の維持メカニズム
当初は転校先の友人関係を保つ目的の金銭窃盗だったが、次第に盗みそのものがストレス発散の目的と移行していったものと思われる。当初、ストレスの発散方法としては家庭内で暴れるといったことがあったが、家庭内の制限の強さから逃れる意味もあり次第に家の外に向くようになり、金銭窃盗へ移行していったという構図もあると思われた。窃盗の段階としては病的窃盗に至っているとはいえず、浅見ら(2021)の先行研究における「行動頻度拡大」の段階といえる。
つまり窃盗が維持されていたメカニズムとしては、友人関係維持のために開始した窃盗行為自体にストレスの発散の意味を見出し、家庭内におけるストレス構造が解決されない中で行動頻度が拡大していったと考えられた。
3.窃盗の終結に向けて
前述まで、Aのもつ窃盗の機能や維持メカニズムについてエビデンスベースに整理していきました。これを元に、Aが窃盗行為を終結させるために、Aが有するリスクを1つ1つフォローしていく流れになると思われます。このリスクについては個別的なアセスメントにより、Aが有しているリスクや窃盗の機能や段階などを具体的に把握し、フォロー方法を詰めていくことが求められます。
Aのリスクと書きましたが、これは当然Aだけでなく、そのAを取り巻く環境のリスクも含まれます。Aだけでなく、Aに関わる人のサポートへの動機付けを行い支援していく、そのような関りが求められて生きます。
具体的なリスクとしては以下のようなもの等が考えられました。
・セントラルエイト リスク・ニーズ要因:レジャー→学校以外の活動への参加
・窃盗の維持変数としての社会的強化:盗みを介した友人関係構築→対人関係構築に課題がある場合は必要に応じたSSTも検討するが、基本的には学校生活の中で自然に友人が作れるよう心理的支援を行い、家庭内外に居場所感を作っていく
・AABリスク:疎外感と親の監護力→親に心理教育+エンパワーメント
・不適応行動のリスク抑制:窃盗に至る機序の言語化とその家族内共有
これらを軸に、AやAの家族に働きかけていきます。例えばAに対しては、窃盗に至る機序の言語化、学校以外の活動への参加の動機付け、などです。家族に対しても上記の関りを軸に働きかけを行っていきます。
エビデンスを元にこのようにアセスメントし、不適応行動等の終結に向けていくことの何が良い点かというと、①勝手な主観・色眼鏡で人の行為を見ない、②効果のない関りを無駄に続けるリスクを下げられる、③すべてを子どものせいにする・子どもに責任を負わせることを避けられる、などがあるんじゃないかなと思っています。特に③ですが、“〇〇だと問題行動のリスクが上がるという研究がある、〇〇の環境を作ったのは君じゃないよね、だから君だけが悪いんじゃないということが科学的にも言えるんだ”と、子どもに伝えることを可能にしてくれるのが、これらの先行研究の存在なのかなと思います。必死に勉強してそれを言える心理司になれるのであれば、膨大な時間を費やしエビデンスを学ぶ価値は大いにある、と思います。
※引用文献は準備中です。すいません…。